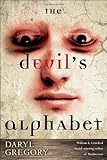The Devil's Alphabet by Daryl Gregory
Del Rey
売り上げランキング: 29108
2009年11月に刊行された新進気鋭のSF/FT作家ダリル・グレゴリイの第2長編。グレゴリイはここ数年短編の分野で頭角を現してきた作家で、2005年の"Second Person, Present Tense"*1、2006年の"Damascus"、2007年の"Dead Horse Point"、そして2008年の"The Illustrated Biography of Lord Grimm"に"Glass"と、毎年何がしかの年間傑作選に作品が収録されている。作風は脳科学とアイデンティティを扱った今風のハードSFから子供時代の夢と現実との齟齬を描く苦めのファンタジイまで幅広い。2008年に出版された第1長編 Pandemonium は、憑依と呼ばれる現象により人々がアメコミのキャラクターのような超常的な力を人々が突然振るう現代のアメリカで、憑依された一人の青年の彷徨を描いたもの。アメコミやSFをはじめポップカルチャーをプロットに織り込む手際、ファンタジイながら脳科学からユング派心理学まで持ち出して論理的アプローチを試みる姿勢、繊細な登場人物達が交わす複雑な愛情と共感、Googleが普通に作中に出てくる同時代的感覚などなど、グレゴリイの作家的特質を凝縮したような作品で、個人的にこの作家に入れ込むきっかけになった。世評的にも好評で、クロフォード賞といういくぶん地味な賞を受賞したほか、シャーリイ・ジャクスン賞、世界幻想文学大賞の長編部門にもノミネートされた。
Pandemonium は優れた作品だけど、分類的にはアーバン・ファンタジイで私のストライクゾーンとは若干ずれていた。ところが第2長編は著者本人曰く「南部ゴシック/SF/殺人ミステリ」で、量子進化がどうとかいう話だという*2。これは是が非でも読まなければと思い、早速読んだのだった。
あらすじ
テネシー州東部の小さな町スイッチクリークで、ある日正体不明の病気が発生する。住民の3分の1が死亡し、残った住民は奇妙な姿に変貌していった。まず身長3mを越す巨人アルゴ、次に禿頭で単為生殖を行うベータ、最後にグロテスクなほど肥満したチャーリー。病気の蔓延がようやく治まったとき、スイッチクリークの住民は3つの系統に分岐していた。住民のDNAに変異が見られたことから、謎の病気はTDS――転写分岐症候群と命名されるが、原因は依然として解明されなかった。マスコミの報道、軍による隔離、近隣町村での暴動やリンチなどを経て、スイッチクリークは次第に無名の一小村へ戻っていった。
パクストンはTDSに感染しながら変異しなかった数少ない人間の1人だった。TDSの発生直後父親に家を追われ、以来シカゴで生活していたパクストンだが、親友であり憧れの女性だったジョー・リンが自殺した知らせを受け14年ぶりに故郷スイッチクリークを訪れる。アルゴになったもう1人の親友ディークや、ベータだったジョー・リンが産んだ双子の女の子に会ったパクストンは、親身ながらも何かを隠しているような彼等の態度に、ジョー・リンの死、ひいてはスイッチクリーク全体への疑念を抱き始める。
そんな中、かつて仲違いした父親と再会したパクストンは、父親がチャーリーで、しかも「熟成」と呼ばれる麻薬性の物質を放出する体質になったのを知る。町の顔役であるロンダ小母が仕切っている「熟成」ビジネスから父親を解放しようとするパクストンだが、偶然「熟成」を大量に浴びたことで依存症に陥り、自らロンダに手を貸すことになる。父親への愛と「熟成」への渇望のあいだでパクストンは苦悩する…。
感想
最初に正直に言うと、やや肩すかしを食らった。いや、自分の期待したものが書いてなかったからといってがっかりするというのも勝手な話だが、第一長編の完成度から考えると今回のはやや不完全燃焼なのでは?と思わずにはいられなかった。
本作も第一長編も、小説の本筋になっているのは主人公の青年がどこか現実と乖離している自分に悩んだり苦しんだりしながら、周囲の人間との関係を通じて自分の居場所を見定めていくというややヤングアダルト風の物語だ。第一長編がこのメインプロットにあれこれ肉付けする形で話を膨らませているのに対し、本作では別のプロットが同時並行的に入り交じってくる。先に述べた著者言うところの「南部ゴシック/SF/殺人ミステリ」である。具体的に話の内容に照らし合わせれば、パクストンと父親の和解が本筋で、そこにロンダ小母の麻薬ビジネスと助成金をめぐる政治的駆け引き(南部ゴシック)、アルゴやベータら各系統の生物学的ディティールや量子力学的解釈に基づくTDS発生の仮説(SF)、ジョー・リンの死の真相(殺人ミステリ)と、大まかに抜き出しただけでも相当多くの内容を盛り込んでおり、推薦文句にKirkus Reviewsの「スティーヴン・キングの最良の作品を想起させる」と書いてあるのもあながちリップサービスではないのではと思うほど、複雑な物語を展開している。ところが終盤これら多様なネタが本筋の後ろに隠れてうやむやのうちに終わってしまい、これは全部のネタをさばききれなかったのでは、とどうしても思ってしまう。特に量子力学関連については中盤本当にちらりと出たきりで不満が募った。ミステリパートに関しても――ミステリには疎いので素人の勘で言っているのだが――あまり冴えた謎解きとは言えないと思う。
もっとも急いで付け加えておくと、そうした全体のバランスの悪さとは別に、グレゴリイの美質はより繊細な部分で遺憾なく発揮されている。文学的SFなどと呼ばれたりもするが、題材があったとして、それを登場人物の対話や議論の中で展開していくのではなく、巧みに登場人物達のシチュエーションに織り込む作家なのだ。例えばパクストンが「熟成」の依存症に陥った折、自分が父親の近くにいたいと思うのは父親を愛しているからか、それとも父親の生み出す「熟成」を脳が欲しているだけなのか、と自分の人間的な面と生物的な面の相剋に悩むシーンなどが典型的だ。またパクストンとジョー・リンの双子の娘達を描くくだりも、単為生殖だから遺伝的なつながりは無いはずなのになぜか疑似親子的な関係が芽生えたりして、そういった不思議な人間(?)関係をうまく捉えるあたりもグレゴリイらしさを感じさせる。
というわけで、振り返ってみればまことこの作家らしい作品であり、文句を付ける筋合いもないのだけど、なぜか一読して不満が残ってしまった。先にも挙げたLocus誌のインタビューで「ファンタジイ的な感触のハードSF」という言い方をしていたため、もっと(私の考える)SFSFした作品を勝手に想像していたせいかもしれない。SF的な部分がうやむやになっていると言ったけれども、Locus誌2009年12月号のゲアリー・K・ウルフの書評ではヴァン・ヴォート『スラン』やスタージョン『人間以上』を引き合いに出しながら「生物学的な謎解きよりも(突然変異の)犠牲者の立場に焦点を当てた進化SF」とまとめている。これがむしろ正面から向き合った読解かもしれない。
いずれにせよ本作でグレゴリイが作家として着実に進歩を遂げていることは確認できた。現在年1作のペースで長編を書いているようだし、いずれ私の好みど真ん中な長編を書いてくれるかもしれないと期待しつつ、次作を待ちたい。
ところで最後に1つ。本作の内容で量子進化がどうのこうのと書いたのだが、これは半分正解で半分間違いだと分かった。"quantum evolution"という言葉には2種類意味があって、1つは古生物学者ジョージ・ゲイロード・シンプソンの使った用語で、詳細はよく分からないが彼の弟子のスティーブン・ジェイ・グールドの有名な「断続平衡説」に似た概念らしい。この場合の"quantum"は「多数・多量」といった意味であり、物理学の「量子」とは関係ない。もう1つはジョンジョー・マクファデンらのいう量子レベルの物質の振る舞いが進化に影響を与えるという、まさしく「量子進化」である。作中ではアルゴ、ベータなど人間と異なる進化の系統が突然発生するあたりが前者の意味、量子力学的解釈からTDSの原因を仮説立てるあたりが後者の意味と、どちらの意味にも取れるようになっている。ハードSFを予備知識なしに本だけ読んでも駄目ですよね…と自戒を込めつつ、メモしておきたい。